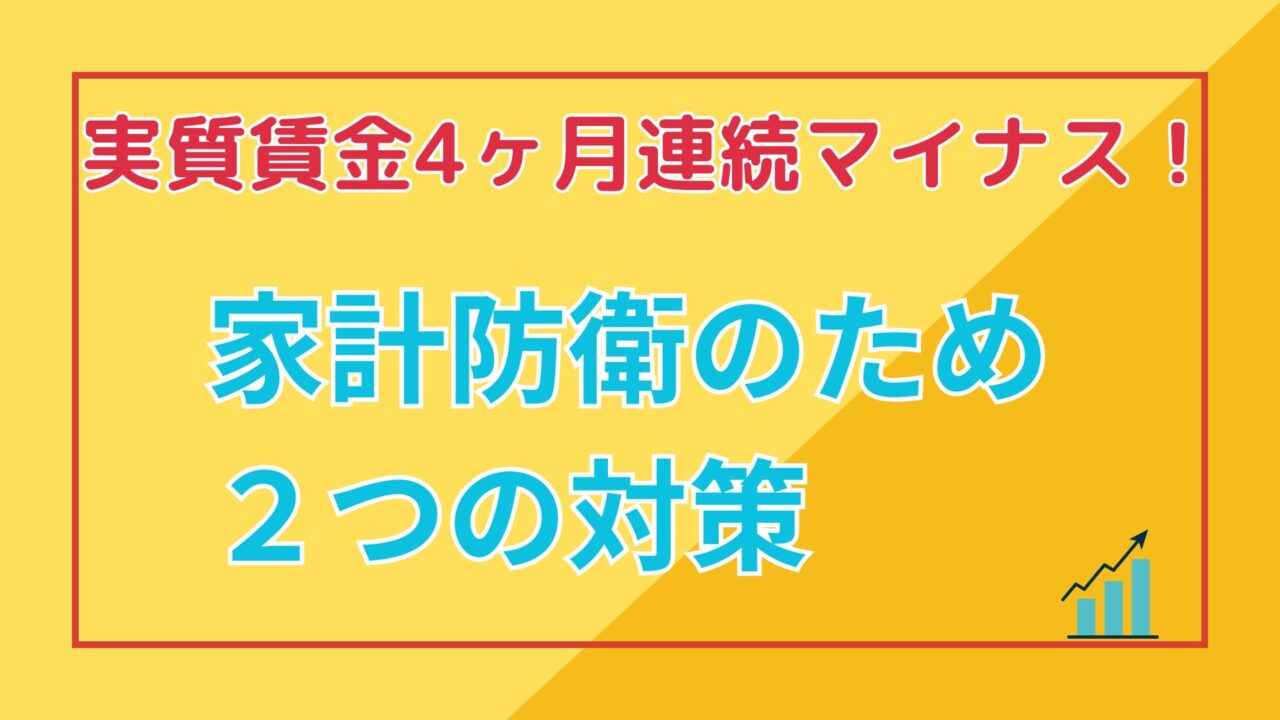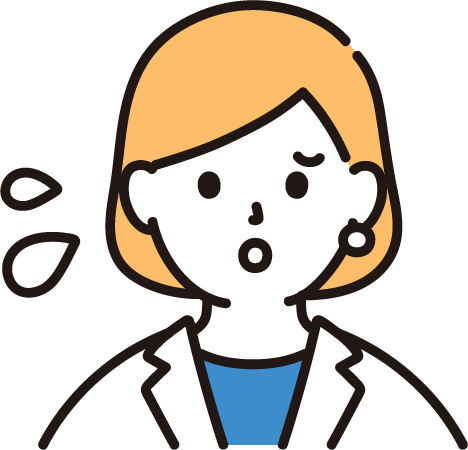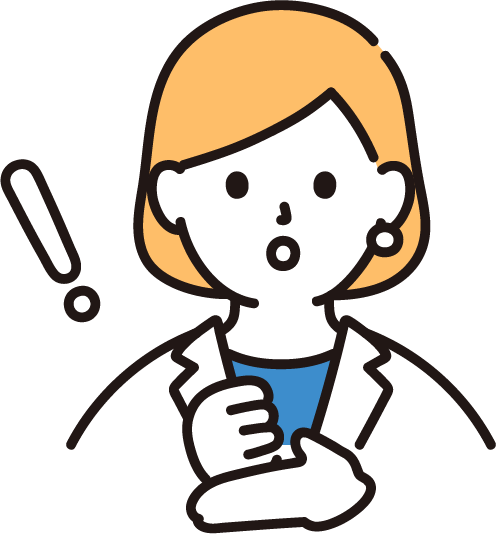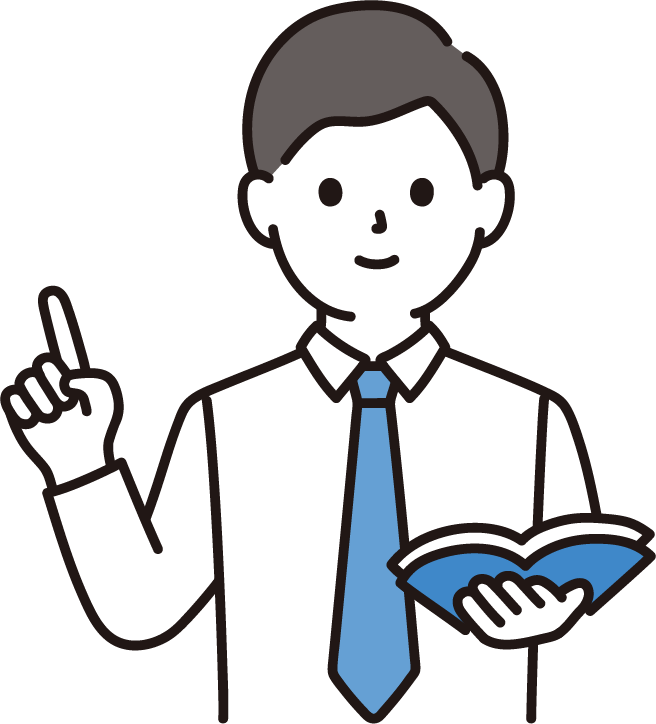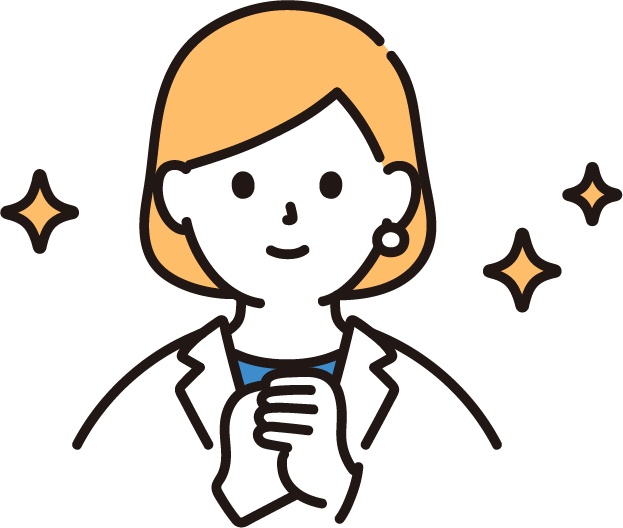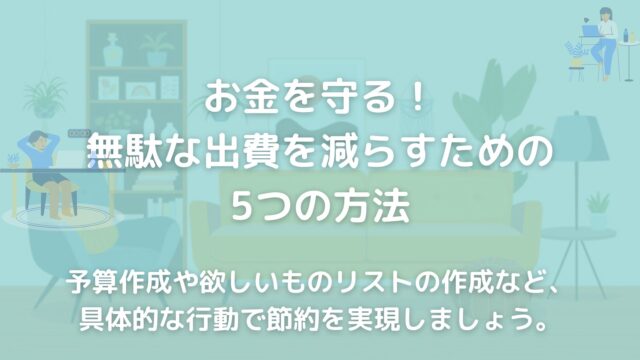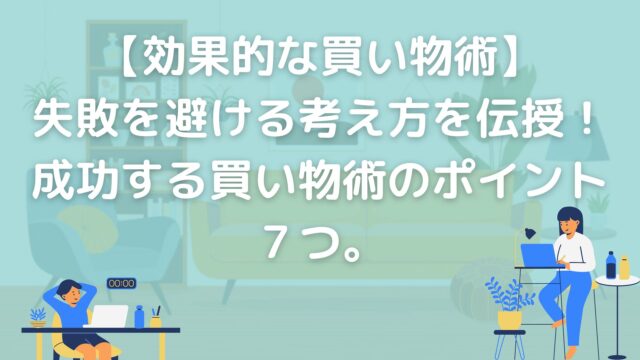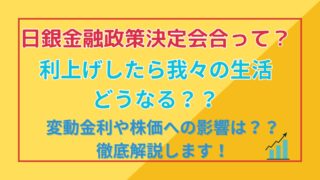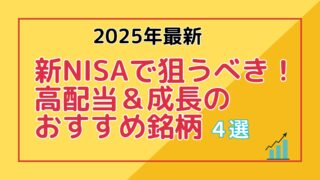最近、物価の上昇が止まらず、家計を圧迫していると感じている方も多いのではないでしょうか。
さらに、実質賃金が4ヶ月連続でマイナスというニュースも流れてきました。
このような情報を聞くと
と不安になりますよね。
そこで今回は、実質賃金低下の現状を分析し、私たちが取るべき具体的な対策について解説していきたいと思います。
- なぜ実質賃金が下がっているのか?
- 賃金が下がっている時に個人でできる対策について
上記の内容について、とても分かりやすく学ぶことができます!
その結果として…
そのように感じていただけたらと思います。

この記事は、節約大好きで投資2年目のFPの資格を持つ私がこれまでの経験をもとに、執筆しています。
参考ニュース 実質賃金 4か月連続マイナス
去年11月 実質賃金 4か月連続マイナス 現金給与増も物価上昇でhttps://t.co/yi9FztrJaa #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) January 8, 2025
実質賃金とは?
「給料で実際にどれだけのモノやサービスが買えるか」を示す指標です。
名目賃金が上がっていても、物価の上昇がそれ以上に大きければ、実質賃金は下がることになります。
例えば…
給料が1万円増えても、物価が2万円分上がっていれば、実質賃金は1万円下がったことになります。
なぜ実質賃金が下がっているのか?
実質賃金が低下している主な要因は、以下のとおりです。
物価上昇(インフレ)
これが最も直接的な要因です。
近年、特に2022年以降、エネルギー価格や食料品などの輸入物価の高騰、円安などの影響で物価上昇が顕著になっており、賃金上昇が追いついていないため、実質賃金が低下しています。
賃金上昇が遅れている
物価上昇に加えて、賃金自体がなかなか上がらないという問題も、実質賃金低下の大きな要因です。これには、以下のような背景があります。
長年のデフレマインド
バブル崩壊後の1990年代後半から、日本経済は長期間にわたるデフレに苦しみました。
この間、企業はコスト削減を最優先し、賃上げを抑制する傾向が強まりました。
このような状況が長年続いた結果、「デフレマインド」が人々の間に根付いてしまったのです。
非正規雇用の増加
非正規雇用は正規雇用よりも賃金が低いことが多く、非正規で働く人が増えると、全体の平均賃金が上がりにくくなります。
非正規雇用の推移はこのようになっています。
- 2000年:約1,400万人
- 2005年:約1,634万人
- 2010年:約1,784万人
- 2015年:約2,000万人
- 2020年:約2,090万人
- 2023年:約2,124万人
実質賃金低下が下がってる!個人で対策できること
実質賃金が低下している状況下で、私たちが個人でできる対策はいくつかあります。
徹底的な家計の見直し
具体的な家計の見直し方法
- 家計簿をつける
- 固定費の見直し
- 変動費の節約
- サブスクリプションの見直し
また、ふるさと納税の活用もお得でオススメです。
収入を増やす努力
支出を減らすだけでなく、収入を増やす努力も重要です。
- 副業を始める
- 資産運用を始める
副業を始める
副業には、単にお金を稼ぐだけでなく、様々なメリットがあります。主な理由を以下にまとめました。
収入アップに直結!生活にゆとりが生まれる
副業の最大の魅力は、なんといっても収入が増えることですよね。
本業の給料に加えて副収入を得ることで、生活にゆとりが生まれ、貯蓄を増やしたり、趣味や旅行にお金を使ったり、生活の質を向上させることができます。
例えば…
このように生活の選択肢が広がります。
自己実現の場になる!好きなことを仕事に
副業は、自分の好きなことや得意なことを活かせる場でもあります。
例えば、
- 絵を描くことが好き→イラスト制作の副業
- 文章を書くのが好き→ブログやライターの副業
など趣味を活かして収入を得ることで仕事へのモチベーションも高まります。
資産運用を始める
複利効果で効率的に資産を増やせる
資産運用の大きな魅力の一つが「複利効果」です。
これは、運用で得た利益を元本に加えて再投資することで、利益が利益を生み、雪だるま式に資産が増えていく効果のことです。
預貯金のように単利で運用するよりも、長期的に見ると大きな差が生まれます。
インフレ対策になる
物価が上昇するインフレ時には、現金の価値が目減りしていきます。
しかし、株式や不動産などの資産は、インフレに合わせて価値が上昇する傾向があります。そのため、資産運用を行うことで、インフレによる資産の目減りを防ぐ効果ことができます。
少額からでも始められる
以前は、まとまった資金がないと始められないイメージがあった資産運用ですが、近年は少額から始められる投資商品やサービスが増えています。
例えば、積立NISAやiDeCoといった制度を活用すれば、月々数千円からでも投資を始めることができます。
投資に関するオススメの記事は以下になります!
まとめ
- 厚生労働省が実施している「毎月勤労統計調査」によると実質賃金は4ヶ月連続でマイナスの状況
- インフレしているのに対して長年のデフレや非正規雇用の増加が賃金上昇の遅れの原因となっている
- 個人では副業や資産運用、家計の見直しなど努力が必要になってくる
実質賃金低下は、私たちの生活に深刻な影響を与える問題です。
個人レベルでは、家計の見直しや収入を増やす努力などを心がけましょう!
この状況を乗り越えるためには、私たち一人ひとりが現状を理解し、できることから行動していくことが大切です。
この記事が、実質賃金低下への対策を考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。